目次
はじめに
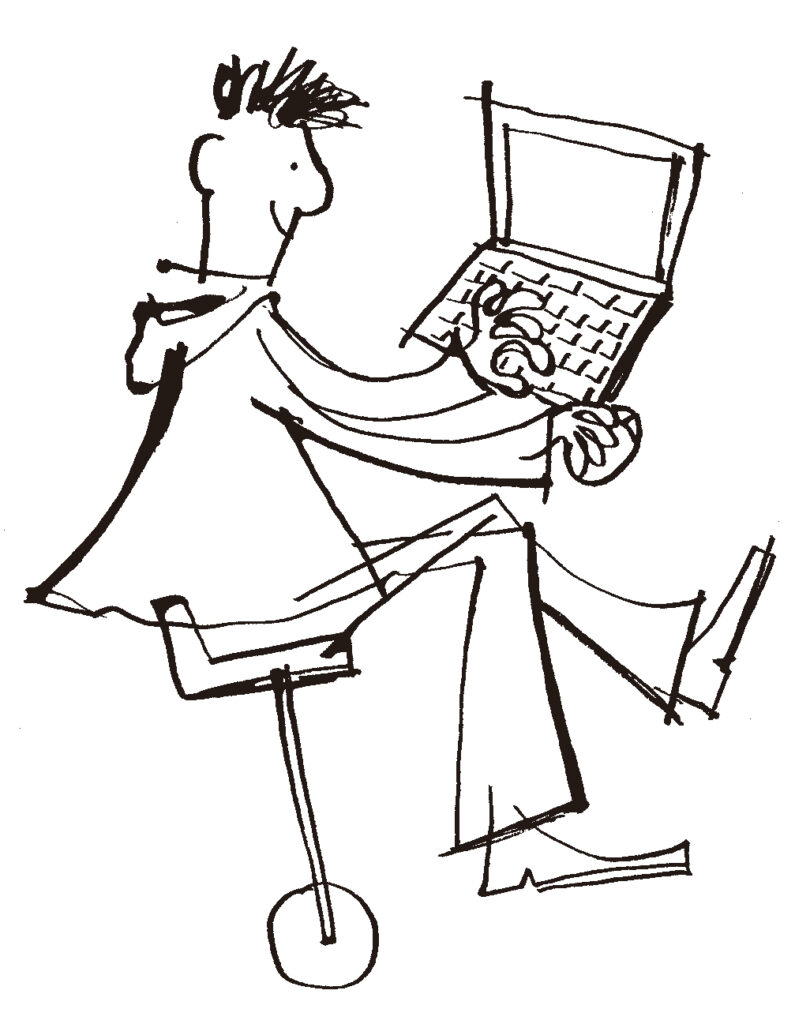
職歴が多い人の職務経歴書は、これまでの経歴をすべて並べるよりも、「どの経験がどうつながっているのか」を整理して伝える書き方を選ぶほうが伝わりやすくなります。
転職回数そのものが評価を下げる決定的な理由になることは少なく、担当してきた仕事の流れや役割の一貫性が読み取れれば、「現場経験を積み重ねてきた人」として実務力の裏付けに受け取られることも多いです。
とはいえ、職歴が多いと、「回数が多い=不利に見られるのでは」と不安になりやすく、どこまで書くべきか、古い職歴も含めてすべて載せるべきか、順番はどうするべきかと手が止まってしまうことがあります。
けれど、採用担当者が実際に見ているのは、履歴書に並んだ社名の数ではありません。どんな部署で、どんな立場を任され、日々どんな業務を積み重ねてきたのか、その中身です。入社年・退社年を時系列に並べるだけだと、肝心のポイントが伝わらず、「この人は何が強みなのだろう」とかえって分かりにくくなる場合もあります。一方で、似た業務や役割ごとに経験を整理し、読む側が頭の中で仕事のイメージを描ける順番でまとめれば、職歴の多さはマイナスにはなりません。
この先では、職歴が多い人が評価を下げずに自分の経験を伝えるために、どんな考え方で整理し、どんな書き方を選ぶと伝わりやすくなるのかを、順を追って見ていきます。
職歴が多いと職務経歴書は本当に不利になるの?
職歴が多いという理由だけで、評価が下がることはありません。採用担当者が見ているのは転職回数の多さではなく、その間にどんな役割を任され、どんなことができるようになったのかが読み取れるかどうかです。
実際に警戒されやすいのは、職歴が多いという事実そのものではありません。「短い期間で、似た理由の退職を何度も繰り返していないか」「担当してきた業務に共通点や流れが見えないのではないか」といった点です。反対に、仕事内容が前の職場から次の職場へと自然につながっていたり、担当範囲が少しずつ広がっている様子が伝われば、職歴の多さは“経験の厚み”として前向きに受け取られます。
不利に見えやすいのは、在籍期間と会社名を時系列に並べただけで、各職場で何を担い、どんな成果を出してきたのかが分からない場合です。この書き方だと、「なぜ転職したのか」「次の職場で何を任せられる人なのか」が想像できず、読み手に小さな不安を残してしまいます。一方で、業務内容を整理し、共通する役割や強みが自然につながる形で示せば、職歴が多くても評価が下がることはありません。
つまり、問題になるのは職歴の数そのものではなく、読む側が状況をイメージできるように整理されているかどうかです。この点を押さえていれば、職歴が多いことだけを理由に書類選考で不利になる心配はほとんどありません。
職歴が多い人はどの書き方を選ぶべき?
職歴が多い場合、在籍した順に漏れなく並べる書き方は、必ずしも適していません。評価されやすいのは、これまでの仕事内容や担ってきた役割のつながりが、自然に伝わる構成です。
時系列だけで整理すると、職場ごとの説明がどうしても細切れになり、「結局、この人はどんな仕事ができる人なのか」が見えにくくなります。特に、短い期間の職歴が続いている場合、理由や背景が書かれていなければ、読み手には状況が想像できず、不安だけが残りやすくなります。その結果、本来伝えたい実務経験の深さよりも、転職回数の多さばかりが目に入ってしまいます。
一方で、業務内容やスキルを軸に整理すると、職歴が多くても話の流れは途切れません。たとえば、複数の職場で同じ職種や近い役割を担ってきた場合、それらをひとまとまりで示すことで、「経験を重ねてきた過程」が自然に伝わります。会社名よりも「何を任されてきたのか」が前に出るため、採用担当者の視線も回数ではなく中身に向かいやすくなります。
職歴が多い人ほど、すべてを同じ重さで書こうとするのではなく、どんな順番で、どんな軸で伝えるかを先に決めることが大切です。書き方さえ間違えなければ、職歴の多さは不利ではなく、実務経験の幅としてきちんと受け取ってもらえます。
具体例①|同じ職種・近い業務が続いている場合
営業職としての経験(通算8年)
・法人向け新規開拓営業、既存顧客フォローを複数社で担当
・業界は異なるが、提案型営業・課題ヒアリング・見積作成まで一貫して対応
・後半は後輩指導、チーム内の案件進捗管理も担当
※在籍会社:A社(2年)/B社(3年)/C社(3年)
→ 会社名よりも「営業として何を積み上げてきたか」が先に伝わり、転職回数が目立ちにくい。
具体例②|役割が段階的に広がっている場合
業務の変化と担当範囲の広がり
・一般社員として実務を担当(データ入力、資料作成、顧客対応)
・業務改善提案、後輩指導を任されるようになる
・進捗管理、関係部署との調整など、管理寄りの業務を担当
※複数社で同様の役割変化を経験
→ 職場が変わっていても、「責任が広がってきた流れ」が一本の線として読める。
具体例③|直近の経験を強く見せたい場合
直近の職務経験(最重要)
・〇〇職として〇年間勤務
・△△業務を中心に担当し、□□のスキルを習得
・現在は□□を主担当として任されている
それ以前の職務経験
・同職種・近い業務内容を複数社で経験
・基礎業務から応用業務まで一通り対応
→ 「今、何ができる人か」が最初に伝わり、過去の職歴は補足として読まれる。
具体例④|やってはいけない書き方
A社(1年)
・営業
B社(8か月)
・営業
C社(1年2か月)
・営業
D社(10か月)
・営業
→ 情報は事実だが、「何が強みか」「どう成長したか」が見えず、転職回数だけが印象に残る。
このように、職歴が多い場合は「どの会社にいたか」ではなく、「どんな経験をどう積み重ねてきたか」が先に伝わる構成を選ぶことが重要です。
書き方を整理するだけで、職歴の多さは不利ではなく、実務経験の幅として正しく評価されます。
職歴が多い人に向いている職務経歴書の型はどれ?
職歴が多い人にとっていちばん相性がいいのは、勤務先を一社ずつ追う書き方ではなく、業務内容や担ってきた役割ごとに整理してまとめる書き方です。この形であれば、採用担当者も短い時間で「この人はどんな強みを持っているのか」をつかみやすくなり、転職回数よりも、実際に積み重ねてきた実務経験が自然と先に目に入ります。
キャリア式が合う人・合わない人
| 区分 | キャリア式が合う人 | キャリア式が合わない人 |
|---|---|---|
| 職種の傾向 | 同じ職種、または近い業務を複数社で続けている | 職種が大きく変わっており、一貫性がない |
| 業務内容 | 営業・エンジニア・事務など、役割やスキルが共通している | 会社ごとに業務内容が大きく異なる |
| キャリアの流れ | スキルや担当範囲が積み上がっている | 経験が点在しており、流れを作りにくい |
| 転職理由の整理 | 業務内容の継続・発展で自然に説明できる | 転職理由が個別事情に依存している |
| アピールしたい点 | 「この分野の実務経験が厚い」こと | 「直近の経験」「今できること」を最優先で見せたい |
| 採用側の理解 | 短時間で強みを把握しやすい | 「今は何ができる人か」が分かりにくい |
| おすすめ度 | ◎ 非常に相性が良い | △ 無理に使うと分かりにくくなる |
同じ職種や、内容がよく似た業務を複数の会社で経験している場合は、キャリア式の書き方が特に向いています。たとえば営業、エンジニア、事務といったように役割が共通していれば、会社名を一社ずつ追うのではなく、「どんな仕事を担ってきたか」を軸にまとめることで、現場経験を重ねてきた流れが自然に伝わります。結果として、「この分野でしっかり実務を積んできた人」という印象を持ってもらいやすくなります。
一方で、職種が大きく変わっていたり、直近の仕事を特に強くアピールしたい場合は、無理にまとめるとかえって分かりにくくなることもあります。読む側が「なぜ方向性が変わったのか」「今は何ができる人なのか」を想像しづらくなるためです。その場合は、まとめ方よりも伝えたい経験がきちんと浮かび上がる形を優先したほうが、安心して読んでもらえます。
逆編年体式を選ぶべきケース
| 判断ポイント | 逆編年体式が向いているケース | 具体的なイメージ例 |
|---|---|---|
| 直近の経験 | 直近の職場での実績・専門性が最も強い | 直近3年で特定分野のエンジニアとして専門業務を担当している |
| 即戦力性 | 「今、何ができる人か」を最優先で伝えたい | 今すぐ任せられる業務内容を最初に把握してほしい |
| キャリアの安定 | 直近の職歴が比較的長く、安定している | 直近の会社に3年以上在籍している |
| 職歴の変化 | 過去より直近で職種・役割が大きく固まっている | 以前は事務・営業など混在、直近は一貫して企画職 |
| 転職回数 | 過去の転職回数を前面に出したくない | 若い頃の短期離職が複数あるが、最近は落ち着いている |
| 採用側の視点 | まず現在のスキルを確認したい職種 | 専門職・経験者採用・ミドル層向け求人 |
| 不安の出にくさ | 直近が明確なら、過去は補足で十分 | 過去より「今の状態」が重視される |
直近の職場での実績や専門性がはっきりしていて、「まずはここを見てほしい」という経験がある場合は、逆編年体式の書き方が合います。いちばん新しい経験から書き始めることで、今の時点で何ができる人なのかが、読み始めてすぐに伝わります。
この形では、直近の仕事が自然と主役になり、それ以前の職歴は背景や補足として受け取られやすくなります。そのため、職歴が多くても過去に意識が向きすぎず、「現在の働き方」や「今の安定感」に目が向きやすくなります。直近のキャリアが落ち着いていれば、転職回数の多さを必要以上に心配されにくい書き方です。
編年体式を使っていい人・避けた方がいい人
| 区分 | 編年体式を選んでいい人 | 編年体式を避けたほうがいい人 |
|---|---|---|
| 転職回数 | 転職回数が少ない(目安:0〜2回) | 転職回数が多い |
| キャリアの流れ | 職種・業務内容が一貫しており、時系列で自然に説明できる | 職種や役割の変化が多く、流れが分断されている |
| 在籍期間 | 各職場の在籍期間が比較的長い | 短期間の職歴が続いている |
| 職務内容の変化 | 前職→次職で段階的な成長が見える | 業務内容が急に変わっている |
| 強みの位置 | 初期の経験から順に読むことに意味がある | 直近の強みが埋もれやすい |
| 採用側の印象 | 時系列で読んでも迷わない | 転職回数や空白期間が目立ちやすい |
| 整理の難易度 | ほぼ整理せずとも伝わる | 整理せずに使うと不利になりやすい |
| 総合判断 | ◎ 問題なく使える | × 他の型を選んだほうが安全 |
編年体式は、転職回数が少なく、キャリアの流れを一本のストーリーとして説明できる場合に限って力を発揮します。経験の積み重ねがシンプルで、前後のつながりがそのまま理解できるときには、読み手も迷わず内容を追えます。
一方で、職歴が多い人が同じ型をそのまま使うと、職場ごとの情報が増えすぎてしまい、どこが大事なのか分かりにくくなりがちです。整理しないまま並べると、強みや実務経験よりも細かな経歴の多さが目につき、「結局この人は何をしてきた人なのか」が伝わりにくくなることもあります。その意味で、使い方を誤ると評価を下げやすい型でもあります。
職歴が多い場合に大切なのは、「どの経験を一番に伝えたいのか」を先に決めてから型を選ぶことです。どの形式を使うかそのものよりも、読む側が立ち止まらずに理解できるかどうかが、結果を大きく左右します。
職歴が多い場合、どこまで書けばいい?
記載例①|評価につながる職歴
〇〇株式会社(在籍:2019年〜2024年)
職種:法人営業
・法人向け新規開拓および既存顧客フォローを担当
・課題ヒアリングから提案資料作成、見積・契約まで一貫して対応
・後半はチーム内の進捗管理、後輩2名の指導も担当
→ 応募先と関連が深く、スキルが積み上がっている職歴は具体的に書く
記載例②|関連はあるが補足的な職歴
△△株式会社(在籍:2016年〜2019年)
職種:営業
・法人向け営業を担当
・基本的な提案業務、顧客対応を経験
→ 役割が重なる場合は要点だけで十分
記載例③|短期間・関連性が低い職歴
□□株式会社(在籍:2015年・約8か月)
職種:事務
・受発注処理、データ入力などの事務業務を担当
→ 在籍事実+業務概要のみ。理由や感情は書かない
記載例④|同じ職種が複数社続いている場合
営業職としての経験(2016年〜2024年/複数社)
・法人向け提案営業を中心に従事
・新規開拓、既存顧客対応、提案資料作成を担当
・後半はチーム内調整や後輩指導も経験
※在籍会社:△△株式会社/〇〇株式会社 ほか
→ 会社ごとに分けず、「経験のまとまり」で見せる
記載例⑤|書きすぎているNG例
A社(1年)
・営業
・テレアポ
・訪問
・資料作成
B社(10か月)
・営業
・テレアポ
・訪問
・資料作成
→ 情報は事実だが、何を評価すればいいか分からない
職歴が多い場合でも、基本として「在籍していた事実」は省かずに書くほうが安心です。ただし、すべての職歴を同じ分量で詳しく説明する必要はありません。
職務経歴書で評価に影響しやすいのは、「書いていないこと」そのものよりも、「どう書かれているか」です。たとえば、在籍していた会社を丸ごと省いてしまうと、年表に空白ができ、「この期間は何をしていたのだろう」と読み手に余計な疑問を持たせてしまいます。反対に、短期間の職歴や応募先と関係の薄い業務まで細かく書き込むと、情報が多くなりすぎて、肝心の強みが埋もれてしまいます。
評価を落とさないためのポイントは、情報に強弱をつけることです。応募先の仕事内容とつながりが深い職歴や、スキルが積み上がっている業務については、担当していた役割や工夫した点が伝わるよう、少し丁寧に書きます。一方で、関連性の低い職歴については、在籍期間と簡潔な業務内容だけにとどめて構いません。また、同じ職種や似た業務が続いている場合は、まとめて記載することで、「経験が途切れずにつながっている」印象を自然に持ってもらえます。
短期間で退職した職歴についても、無理に消す必要はありません。事実としてきちんと記載し、どんな業務に携わったのかを簡潔に示しておけば、それだけで大きな問題になることはほとんどありません。大切なのは、「この経験が今の仕事にどうつながっているのか」が、読み手に伝わる状態になっているかどうかです。
職歴が多い人の職務経歴書で意識したいのは、単に量を減らすことではありません。読む側が迷わず理解できるように、情報の密度を整えることが、いちばん伝わりやすい書き方です。
職歴が多くても評価される人はどう整理している?
評価されやすい職務経歴書に共通しているのは、職歴を「在籍した会社の数」として並べるのではなく、「どんな経験を積み重ねてきたか」というまとまりで整理している点です。読む側は社名を追わなくても、仕事の内容や役割の流れを一目で思い描くことができます。
その結果、転職回数そのものが強く意識されにくくなり、「いくつの職場を経験したか」よりも、「どんな実務を積み上げてきた人なのか」が自然と伝わります。回数が多く見えないのは、経験の流れが分かりやすく整理されているからです。
同じ業務内容はまとめてもいい?
例①|営業職を複数社で経験している場合
営業職としての経験(通算8年/複数社)
・法人向け新規開拓営業および既存顧客フォローを担当
・顧客課題のヒアリングから提案資料作成、見積・契約まで一貫して対応
・業界は異なるが、提案型営業としての基本業務は共通
・後半は後輩指導、チーム内の進捗管理も担当
※在籍会社:A社(2年)/B社(3年)/C社(3年)
→ 会社名より「営業として何ができるか」が先に伝わる
例②|エンジニア・開発系で業務内容が近い場合
開発業務としての経験(通算5年/複数社)
・Webアプリケーションの設計・実装・テストを担当
・要件定義の補助、既存機能の改修、新機能追加に対応
・使用言語・環境は異なるが、基本的な開発工程は共通
※在籍会社:D社/E社
→ 転職回数ではなく「開発経験の厚み」が残る
例③|事務・バックオフィス系の場合
事務職としての経験(複数社)
・受発注処理、データ入力、請求書作成などの事務業務を担当
・社内外の問い合わせ対応、資料作成を経験
・業務効率化を意識した運用改善にも関与
→ 「事務を何社でやったか」ではなく「どこまで任せられるか」が伝わる
同じ職種や、内容の近い業務を複数の会社で担当している場合は、一社ずつ細かく分けて書くよりも、まとめて記載したほうが評価されやすくなります。たとえば「営業職としての経験」「開発業務としての経験」といった形で整理すると、どんなスキルを積み上げてきたのかが分かりやすくなります。
この書き方であれば、会社が変わった事実よりも、「その仕事を通じて何ができるようになったのか」が前に出ます。読む側も職場ごとの差異に気を取られず、「この人はどんな役割を任せられる人なのか」を短時間で把握しやすくなります。
役割が変わっただけの転職はどう書く?
例①|一般社員 → リーダーへ役割が変わった場合
営業職としての経験(通算7年/複数社)
・当初は一般社員として法人向け営業を担当
・提案業務の安定運用を評価され、後輩指導を任されるようになる
・その後、チーム内の案件進捗管理や業務調整も担当
※複数社で同様の役割変化を経験
→ 会社が変わった理由を書かなくても、「役割が広がった流れ」が読める
例②|実務担当 → 管理寄りの役割に移った場合
業務範囲の変化と担当役割
・実務担当として日常業務を中心に対応
・業務改善提案や調整業務を担うようになり、管理寄りの役割へ移行
・進捗管理、関係部署との連携を担当
→ 転職=方向転換ではなく、役割のステップアップとして読める
例③|同職種だが「専門寄り」に変わった場合
〇〇職としての経験(通算6年)
・前半は幅広い業務を担当
・後半は特定領域(△△)を中心に担当し、専門性を強化
・より専門的な業務を担うため、担当範囲を明確にした職場へ移行
→ 「環境を変えた」ではなく「役割を深めた」転職として伝わる
NG例|やってはいけない書き方
A社
・営業
B社
・リーダー
C社
・管理
→
- なぜ役割が変わったのか分からない
- その結果、転職理由を想像させてしまう
職場がいくつ変わっていても、担ってきた役割や担当範囲が近い場合は、会社名ではなく業務内容を軸に流れを組み立てると伝わりやすくなります。たとえば、最初は一般社員として実務を担当し、次に後輩指導や小さなチームのまとめ役を任され、さらに進捗管理や調整業務など管理寄りの役割へ広がっていった場合、その変化が段階的に分かるよう整理します。
このようにまとめることで、職場が変わった事実よりも、「どんな経験を積み、どこまで任されるようになったのか」が自然に伝わります。読み手も、転職の多さではなく、責任や役割が少しずつ広がってきた流れとして受け取りやすくなり、キャリアアップの過程として無理なく理解できます。
「点」に見える職歴を「流れ」に変えるやり方
職歴が多いと、経歴が一つひとつ独立した「点」のように見えてしまうことがあります。これを避けるためには、前後の職歴に共通する要素を意識して整理することが効果的です。たとえば、使ってきたスキルや担当してきた業務内容、関わってきた領域をそろえて書くだけでも、職歴はばらばらではなく、一本の流れとして伝わります。
職歴の整理で採用担当者が重視しているのは、「途中で引っかからずに読み進められるかどうか」です。経験のつながりが自然に理解できれば、職歴の多さそのものが評価を下げる理由になることはありません。むしろ、どんな実務を積み重ねてきた人なのかが、無理なく伝わる書き方になります。
最初の数行で何を書けば安心して読んでもらえる?
職歴が多い人ほど、冒頭の数行で「この人はどんな仕事ができる人なのか」をはっきり伝えておくことが大切です。最初に強みや専門性の方向性が見えないと、その後にどれだけ丁寧に職歴が整理されていても、採用担当者は「結局、何を任せられる人なのだろう」と迷いながら読み進めることになります。
逆に、冒頭で役割や得意分野が具体的に示されていれば、そのあとの職歴は確認作業として落ち着いて読んでもらえます。職歴の多さそのものよりも、「最初に何が伝わるか」が、読む側の安心感を大きく左右します。
職務要約がないと、なぜ不利になる?
職務要約がない職務経歴書は、いきなり細かな経歴の説明から始まってしまうため、採用担当者は最初の段階で全体像をつかめません。特に職歴が多い場合、「この人はどんな経験を強みとしているのか」が見えにくくなり、内容を理解する前に転職回数だけが印象に残ってしまうことがあります。
最初に方向性が示されていないと、読む側は一つひとつの職歴を確認しながら、「この経験はどこにつながるのだろう」と考え続けることになります。その結果、本来伝えたい実務経験や専門性よりも、経歴の多さに意識が向いてしまいやすくなります。職歴が多いほど、冒頭で全体像を示しておかないと、強みが埋もれてしまうのです。
職歴が多い人ほど最初に書くべき一文
最初に書いておきたいのは、職種・経験年数・主な担当領域をひとまとめにした一文です。たとえば「営業職として〇年間、法人向けの提案から既存顧客のフォローまでを一貫して担当してきました」というように、どんな軸で仕事をしてきたのかを先に示します。
この一文があるだけで、採用担当者は「この人はこういう分野の経験を積んできた人なんだな」と最初にイメージを持つことができます。その後に続く職歴も、ばらばらの経歴ではなく、その軸を補足する情報として自然に読み進めてもらえるようになります。
長くなりすぎない要約の目安とは
職務要約は、長く書けば評価が上がるものではありません。目安としては200〜300字ほどで、これまでの経験に共通する軸や強みが伝われば十分です。具体的な成果や数字、細かな業務内容は後半に譲り、冒頭では「どんな分野で、どんな経験を積んできた人なのか」がすぐに分かる状態をつくります。
最初の数行が整理されていれば、職歴が多くても不安を持たれることはありません。採用担当者が安心して先を読み進められる入口を用意できているかどうかが、評価を分ける大きなポイントになります。
転職回数が多い理由は、どこまで触れるべき?
転職回数が多い理由については、職務経歴書の中で細かく説明しすぎる必要はありません。背景を長々と書くよりも、事実関係が自然に伝わる程度に触れておくほうが、読み手に余計な負担をかけずに済みます。
採用担当者が知りたいのは、事情の細部よりも、「この人は今、どんな状態で、どんな仕事ができるのか」という点です。理由の説明に力を入れすぎると、かえってそこに目が向き、不安を想像させてしまうこともあります。必要以上に強調せず、職務内容や経験の流れの中でにじませるくらいが、ちょうどよいバランスです。
大切なのは、読み終えたときに違和感や引っかかりが残らないことです。転職理由の説明よりも、安心して次のページを読み進めてもらえるかどうかを優先することが、評価につながります。
理由を書かないと不安に思われる?
転職理由をまったく書かなくても、それだけで評価が下がることはありません。採用担当者も、すべての事情が職務経歴書に書かれているとは考えていないためです。
ただ、短期間の職歴が続いている場合に、その背景が何も見えない状態だと、「同じ理由で辞めることを繰り返しているのではないか」「職場に定着しにくいのではないか」といった疑念を持たれやすくなります。これは理由を書いていないこと自体よりも、読み手が状況を想像できないことによる不安です。
ここで大切なのは、説明を長く書くことではありません。細かな事情や感情まで語らなくても、「業務内容の変化」「役割の区切り」「環境の整理」といった形で背景がうっすら伝われば、採用担当者は納得して読み進めることができます。
つまり、求められているのは情報量ではなく納得感です。読み終えたときに引っかかりが残らなければ、それ以上の説明は必要ありません。
書かないほうがいい転職理由とは
人間関係への不満や会社への批判、待遇面の不満をそのまま書いてしまうと、転職回数の多さと結びついて受け取られやすく、マイナスの印象につながりがちです。また、事情を細かく説明しすぎると、「納得してもらおうとしている」「言い訳をしている」と感じさせてしまうこともあります。
職務経歴書で求められているのは、感情の背景や評価ではありません。どんな環境で、どんな役割を担い、何を経験してきたのかが伝われば十分です。個人的な不満や気持ちに踏み込まず、事実と業務の流れに集中したほうが、読み手は安心して内容を受け取ることができます。
前向きに見える理由の共通点
評価を落とさずに理由を伝えるためには、転職が業務内容や役割の変化と自然につながっていることが大切です。たとえば、担当領域が少しずつ広がっていった、特定の分野の専門性を深める必要があった、業務環境が変わり次の役割へ進んだ、といった流れが読み取れるだけで、転職回数そのものは十分に理解されます。
細かな事情まで書き込まなくても、「次の職務内容とどう結びついているか」が見えれば、採用担当者は納得して読み進めることができます。具体的な背景や判断理由は、必要に応じて面接の場で補足すれば問題ありません。
転職理由は、職務経歴書の主役ではありません。あくまで中心にあるのは、どんな経験を積み、その経験がどうつながってきたかです。その流れがきちんと伝わっていれば、理由の説明は最小限で十分です。
職歴が多い人がやりがちなNGな書き方
職歴が多い人ほど、「やってはいけない書き方」を避けるだけで、評価は大きく変わります。経験や実績そのものに問題があるのではなく、見せ方を誤ったことで、本来の強みが正しく伝わらず、不利に見えてしまうケースは少なくありません。
逆に言えば、余計な不安を招く書き方さえ避けられれば、職歴の多さはそれだけでマイナスにはなりません。内容を変えなくても、伝え方を整えるだけで、受け取られ方は大きく変わります。
職歴を羅列するだけになるパターン
NG例|職歴をただ並べているだけの書き方
A株式会社(2018年4月〜2019年3月)
・営業
・新規開拓
・既存顧客対応
B株式会社(2019年6月〜2020年2月)
・営業
・新規開拓
・既存顧客対応
C株式会社(2020年5月〜2021年4月)
・営業
・新規開拓
・既存顧客対応
D株式会社(2021年7月〜2023年3月)
・営業
・新規開拓
・既存顧客対応
会社名・在籍期間・業務内容をすべて同じ調子で並べてしまうと、情報に流れが生まれず、採用担当者はどこに注目すればいいのか分からなくなります。特に職歴が多い場合、一つひとつの重みが同じに見えてしまい、「結局どれが重要なのか」がつかめません。その結果、仕事内容よりも転職回数ばかりが印象に残ってしまいます。
経験のつながりが見えない書き方は、それだけで読み手に小さな不安を与えます。どんな実務を積み、どう成長してきたのかが追えなければ、「この人は次に何ができるのだろう」と立ち止まらせてしまうのです。職歴が多い人ほど、情報をただ並べるのではなく、流れが伝わる形に整えることが欠かせません。
すべて同じ分量で書いてしまった場合の失敗例
失敗例|すべて同じ分量で書いている職務経歴書
A株式会社(2016年4月〜2018年3月)
職種:営業
・法人向け新規開拓営業を担当
・既存顧客のフォローを担当
・提案資料の作成、見積対応を実施
・社内外の調整業務を担当
B株式会社(2018年6月〜2019年5月)
職種:営業
・法人向け新規開拓営業を担当
・既存顧客のフォローを担当
・提案資料の作成、見積対応を実施
・社内外の調整業務を担当
C株式会社(2019年8月〜2021年7月)
職種:営業
・法人向け新規開拓営業を担当
・既存顧客のフォローを担当
・提案資料の作成、見積対応を実施
・社内外の調整業務を担当
D株式会社(2021年10月〜2023年3月)
職種:営業
・法人向け新規開拓営業を担当
・既存顧客のフォローを担当
・提案資料の作成、見積対応を実施
・社内外の調整業務を担当
評価につながる職歴と、補足的な位置づけの職歴を同じ分量で書いてしまうと、本来伝えたい強みが埋もれてしまいます。どの経験も同じ重さで並んでいると、採用担当者は「どこを評価すればいいのか」が分からず、判断に迷ってしまいます。
重要な経験ほど、担当していた役割や工夫した点が具体的に伝わるよう書き、そうでない職歴は要点だけを簡潔にまとめます。この強弱があることで、読む側は自然と注目すべき部分に目を向けることができます。強弱のない書類は、情報量が多くても「何を評価すればいいのか分からない職務経歴書」になってしまいます。
「説明しすぎ」が逆効果になる理由
転職理由や背景を丁寧に伝えようとして説明が長くなると、どうしても言い訳のような印象が強くなりがちです。職務経歴書は、事実と担ってきた役割を伝えるための書類であり、感情や個別の事情を詳しく語る場ではありません。必要以上に説明を重ねると、かえって読み手の不安を広げてしまうこともあります。
職歴が多い人がつまずきやすいのは、経験の内容そのものではなく、整理が足りていない点です。「書かないように工夫する」ことよりも、「どう整えて見せるか」を意識できているかどうかが、評価を大きく分けます。経験を減らすのではなく、伝わる形に整えられているかが重要です。
職務経歴書を書き終えたあと「必ず確認したいポイント」
完成した職務経歴書は、内容の良し悪しそのものよりも、「採用担当者が迷わず読めるかどうか」で最終的な評価が決まります。どれだけ経験や実績がそろっていても、読み進める途中で立ち止まってしまうと、その強みは十分に伝わりません。
特に職歴が多い場合、この確認を怠ると、「どこを評価すればいいのか」「何を強みとして見てほしいのか」が採用担当者に伝わらなくなります。せっかく整理したつもりでも、採用担当者の視点で読み返してみると、意図が埋もれてしまっていることも少なくありません。読み終えたときに迷いが残らないかどうかが、最後の評価を分けるポイントになります。
この職務経歴書、5秒で理解できる?
模範例|5秒で理解できる職務経歴書
職務要約
法人営業として8年間、BtoB向けの提案営業に従事してきました。新規開拓から既存顧客フォローまで一貫して担当し、後半は後輩指導や案件進捗管理など、リーダー寄りの役割も経験しています。
営業職としての経験(通算8年/複数社)
・法人向け新規開拓営業、既存顧客フォローを担当
・顧客課題のヒアリングから提案資料作成、見積・契約まで対応
・業界は異なるが、提案型営業としての業務内容は共通
・後半は後輩2名の指導、チーム内の進捗管理も担当
※在籍会社:A社(2年)/B社(3年)/C社(3年)
直近の職務経験
C株式会社(2021年〜現在)
・主に既存顧客を担当
・大型案件の提案、関係部署との調整を担当
・チーム内の業務分担・進捗管理を任されている
最初に目に入る職務要約と直近の経験だけを読んで、「この人はどんな仕事ができる人なのか」がすぐに伝わる状態が理想です。採用担当者は、まずその部分で全体の方向性をつかもうとしています。
もしここで立ち止まられてしまう場合、情報が足りないのではなく、伝える順序や強調すべきポイントがずれている可能性が高いです。最初の段階で役割や強みの軸が見えれば、その後の職歴は確認として落ち着いて読まれます。逆に、入口で迷わせてしまうと、どれだけ中身が整っていても評価につながりにくくなります。
採用担当者の視点で不安が残る場所はない?
転職が短期間で続いている箇所や、業務内容が急に切り替わっている部分について、採用担当者の視点で「説明が足りていないと感じないか」を確認します。ここで意識したいのは、事情を長く書き足すことではありません。
大切なのは、前後の職歴に共通する業務内容や、担ってきた役割の継続性が自然に読み取れる表現になっているかどうかです。仕事の軸や経験のつながりが見えれば、短期間での転職や変化があっても、採用担当者は立ち止まらずに理解できます。説明量ではなく、流れが伝わっているかを基準に見直すことが重要です。
応募先ごとに調整すべき点は?
職務経歴書は、一度作って終わりにするものではありません。応募先の仕事内容に近い経験が、自然と目に入る順番になっているか、逆に今の応募先では評価につながりにくい情報が前に出ていないかを、改めて見直します。内容を書き足さなくても、並び替えをするだけで、採用担当者の受け取り方は大きく変わります。
最終的に目指したいのは、職歴の多さそのものを意識させず、「どんな経験を積んできた人なのか」という流れだけが残る状態です。この確認ができていれば、書類選考で不利になる要素はほとんど残りません。
まとめ
職歴が多い人の職務経歴書で最も重要なのは、「転職回数をどう隠すか」ではなく、「経験の流れが自然に伝わるかどうか」です。転職回数そのものが評価を下げることはほとんどなく、採用担当者が不安を感じるのは、経験が整理されず、全体像がつかめない書き方をしている場合です。
職歴が多い場合でも、業務内容や担ってきた役割を軸にまとめ、冒頭の数行で強みや方向性を明確に示せていれば、採用担当者は迷わず読み進めることができます。すべての職歴を同じ分量で並べるのではなく、評価につながる経験を前に出し、補足的な職歴は簡潔に扱うことで、実務経験の厚みだけが自然に残ります。転職理由についても、詳しく説明しすぎる必要はなく、業務のつながりが読み取れる範囲にとどめれば十分です。
職務経歴書は、職歴の多さを正当化するための書類ではありません。採用担当者が「この人にどんな仕事を任せられるのか」をすぐにイメージできる状態になっていれば、職歴が多いことは不利にならず、むしろ経験の豊かさとして前向きに受け取られます。